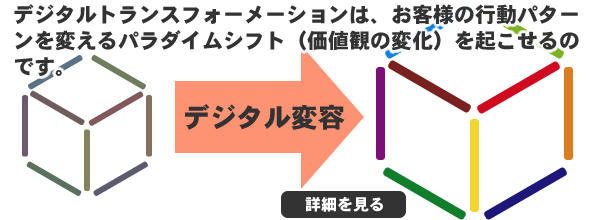コンピュータプログラムの著作権について考えてみたい
コンピュータプログラムの著作権について考えてみたい。
すべての創造物にはそれを作った人の権利がある。
なぜあるかと言えば、著作権法により規定されているからだ。
他人が作ったものを真似して同じものを作ることは難しい。
同程度の技術がなければ真似できないからだ。
しかし、本に書かれた物語はどうだろう。
一般的な教育を受けた人なら誰でも同じように文字を書くことができてしまう。
そこで必要となったのが、作者に許可を得ないで真似しちゃダメだよというルールだった。
ルールを作っても守らない人がいるので罰則も作った。
著作者の権利を侵害したら自由を奪われたり、みせしめに労役につけさせたりすることにした。
それが日本の著作権法。
特許とは違い、特許庁に申請したりする必要はない。
何かを創造したら自然に権利が与えられる。
素晴らしい世の中だ。
しかし著作権も所有権と同じように対価によって他人に譲渡することができる。
絵画を買って、その絵画の著作権が自分のものになったのだと誤解する人はいないだろう。
しかしことコンピュータプログラムの場合には、ほとんどのプログラマーが企業と雇用契約を結んでいる。
このため、著作権法の職務著作という規定によって著作権は企業側に取られてしまっていた。
プログラマーが脱サラして個人事業主としてあるいは法人として依頼者と契約する場合にも、弱い立場だったプログラマーは依頼主の提示する契約書の雛形のまま著作権は依頼主に譲渡するという内容の契約書に調印してしまっていた。
プログラマーという職業が生まれて40年ほどになるが、ずっと依頼主は大企業だった。
コンピュータが中小企業に普及しても、そこでは汎用品のパッケージソフトが使われるだけだったのでプログラマーの出る幕はなかった。
2010年代になってようやく小規模企業や個人がプログラマーにアプリの作成を依頼するような環境が整った。
そこでは注文者とプログラマーがフラットな関係であるため、プログラマーが率先して著作権について注文者に説明する必要が出てきた。
プログラマーは当然著作権が自分にあることをウェブサイト等で説明し、無断改変は刑事責任の罪になることを記載する必要がある。
もちろん、著作権が欲しいという注文者には対価を請求することになる。
所有権と著作権は違うということ。
人身売買のようなSES契約をしたいのなら何も言わない。
ただ自律的、職人的に働きたいのなら、注文者へどういうライセンスでアプリを提供するのかを考えてみるといいだろう。
<参考>
http://www.webbanana.org/#license