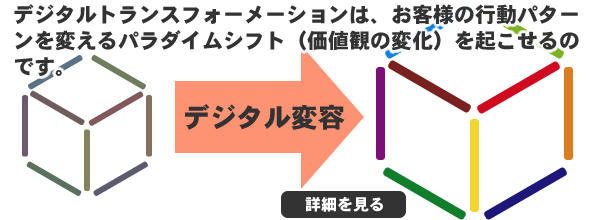縄文と弥生そして天皇と有力者の二重支配の原点について考えてみる
縄文と弥生そして天皇と有力者の二重支配の原点について考えてみる
普通に考えれば、次のような区分けになる。
<縄文> <弥生>
文化センスが高い 稲作、養蚕
国津神 天津神
スサノオ、大国主 アマテラス
関東 関西
出雲(島根県) 日向(宮崎県)
長頭 短頭
弥生人に滅ぼされた?天皇家の祖先?
最後の項目にあるように、一般的には大なめ祭など天皇が行う儀式を見ても稲作が豊作になることを祈願するものが多く、普通に考えれば天皇などの皇室は弥生人と思われる。
しかし、写真画像が残る明治以降の天皇家の人々の横顔を見ると、縄文人の大きな特徴である「長頭」が多いことがわかる。
日本列島がユーラシア大陸と地続きだった頃(2万年より前の時代)に日本で暮らし始めた縄文の人々は人数が多かった。
三千年前に船で日本にやってきた弥生人はその人数が限られていた。
寒冷化によってユーラシア大陸を旅立つことを選択した弥生の人々は、穀物のタネをもって、温暖で暮らしやすい日本にやって来た。
日向などの海岸近くの平野を耕作して穀物を作っていた弥生の人々を見て、縄文の人々は羨ましかったに違いない。
そのタネをもらい耕作方法を学ぶ中で、弥生人が「上」で縄文人が「下」という上下関係ができた。
弥生の人々が大多数の縄文の人々を平和裡に従属させるために行ったこと、それは、その三千年後に日本国で内乱やゲリラ活動が起きないように、米国人が日本人を占領するために用いた方法と全く同じ手法だった。
縄文の人々が信奉する縄文の長を王としてそのまま担ぐことで、縄文対弥生の戦いをせずに実権だけを弥生の人々が担うことを選んだ。
弥生時代の弥生人
飛鳥時代の蘇我氏
奈良時代・平安時代の藤原氏をはじめとする貴族と呼ばれた人々
鎌倉時代の源氏・北条氏
室町時代の足利氏
安土桃山時代の織田氏・豊臣氏
江戸時代の徳川氏
明治時代の薩摩藩長州藩による政府
大正時代の大正政府
昭和時代の昭和政府・自由民主党政府
平成時代の自由民主党政府
弥生時代以降、天皇家はアイコンとして君臨していただけで、実権はその時代時代の有力者が政治を行って来たのである。
その権威と権力を分離した二重支配とも言える構図は、縄文の人々から弥生の人々に有力者が変わった、いわゆる「国譲り」と呼ばれている有力者の変化から始まった日本独特の文化そのものなのである。
二重支配構造が他の国々には全く見られない日本独特の仕組みなのは、人々が暮らす日本列島が1億2千万もの人々が平和に暮らすことを許容する環境だったことがもたらしたものなのである。