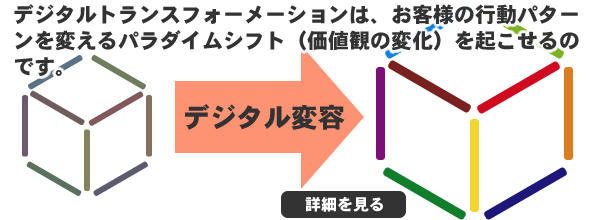和と日本、二つの国の文化が融合したものが日本文化なのである
三千年以上前から、世界中でいくつもの国が勃興衰退を繰り返して来た。
ここ日本では万世一系で、ずっと昔から一つの王家で一つの国だった。民族も一つ大和民族だと。
これが日本書紀古事記をベースとした考え方だった。
近年になり、奈良で書かれた日本書紀古事記以外の伝承を記した書物が世の中に出てくるようになった。
邪馬台国やヤマトとして知られる千年以上前の古代の日本には、唯一、奈良が国家の中央で関東や東北北海道は日本の辺境で国家はもとより存在せず、文化も劣った地域で中央の奈良から蝦夷と呼ばれ蔑まされていたというステレオタイプの観念が否定された。
心がふるえるような作品である「火焔土器」やウルシをぬり色鮮やかなクシなどの装飾品が現在に残されている、いわゆる縄文文化を形成した縄文の人々は「言葉も文字も国家すら持たずウガウガ言っているだけの原始人」だとこれまでは思われてきた。
1万2千年前の縄文時代の日本人が使っていたものに見えますか?

鳥浜貝塚の赤色漆塗り櫛
福井県立若狭歴史博物館より引用
江戸時代頃まで諸国に伝承されていた記憶によると、青森から諏訪までの東日本地域はヒノモトノクニとして奈良にあったヤマトとは人種的にも全く別の国家があったことがわかった。
日本の国歌や国旗がつい最近まで定義されていなかったのはなぜなのか、それがなぜ白地に太陽の文様であるのか疑問があった。
空は青いし、海の水平線も青い、白い曇った空には太陽はでないからだ。
背景が白で太陽が出るという状況はない。
なのになぜ大変な労力をして背景色を白に漂白した旗を作ったのかと。

紙本著色清水寺縁起、田村麻呂の蝦夷(えぞ)討伐
e国宝より引用
江戸時代頃まで諸国に伝承されていた記憶では、大雪が一面に広がった大地に太陽が昇る光景を表現した文様がつい最近国旗となった「日の丸」のデザインモチーフだったことがわかった。
胸のつかえが下りる思いがした。
青森から諏訪までの東日本地域に、三千年以上前にあったヒノモトノクニのデザインモチーフだったため、平成になるまで、ここ日本国には国旗も国歌も定義されていなかった。
平成まで続く、奈良中央のヤマト国家、その国旗ではなかった「日の丸」や「ヒノモト」という国名を流れで使うことになったため、国家として「日の丸」を国旗として定義しにくかったのである。
中国の歴史書にヤマトを表す「倭」とは別の国として「日本」の様子が記されていることは知っていたが、具体的にその「日本」がどこにあったのかはわからなかった。
縄文海進として知られているように二万年前から三千年前までの日本を含む世界は温暖化真っ只中だった。
シベリアにマンモスが住めたような時期だ。
日本の国土特に東日本地域は酸性土のため人を含む生物の化石が残りにくい。
日本書紀古事記には、蝦夷として征伐すべきワルモノとして詳細は何も記されていない諏訪・東海より東の地域にはもうひとつの本当の日本の国があったという記憶が、江戸時代まで諸国の人々に伝承されていたのである。
現在、「極東」と欧州からいわれているここ日本列島は、三千年以上前、樺太、北海道とともに陸続きだったロシア・モンゴルの人々と頻繁に通商を行い、接するうちに「太陽が出る方角である東の果てという意味の「日本」」として自分の国のアイデンティティを深めていったのだ。
そして、縄文の人々はヒノモト「日本」と自らの国をなのった。
-
ここからは私の考えを述べてみたい。
日本には一つで事足りるのにも関わらず、二つのものが存在することがある。
・カナ
ひらがなとカタカナ
・数字の読み方
一二三四五六七八九十
いちにさんしごろくひちはちきゅうじゅう
ひふみよいつむななやここのつとお
・音表
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやいゆえよらりるれろわいうえをん
イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネナラムウイノオクヤマケフコエテアサキユメミシエイモセス
・国土
長野〜静岡のフォッサマグナを境に二つの島がくっついた本州
・土器デザイン
縄文と弥生
・文化
関西丸餅を煮る、関東角餅を焼く
・Y染色体遺伝子
長野を境に遺伝子が別
・国名
ワとニホン
和と日本
・日本の発音
にっぽんとにほん
*国名の発音が習慣的にも法的にも決まっていない国が、果たして日本以外にあるだろうか?
・古代の神
天津神と国津神
これらは二つの文化が融合したものが、日本文化そのものであること如実に示していると考えている。