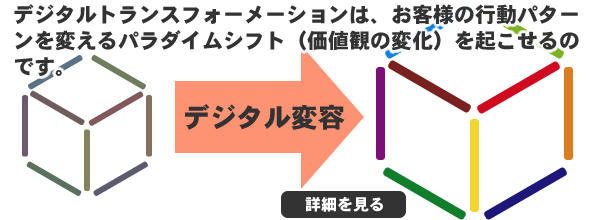埼玉稲荷山古墳金錯銘鉄剣その漢文の新解釈
埼玉稲荷山古墳から出土された金錯銘鉄剣に金により象嵌された文字について
2017年2月24日
この鉄剣は1960年代に発掘された。
ただの鉄剣だと思われていたが、1970年代にx線に偶然かけられ、その時に金象嵌という珍しい処置が施されていることが分かり、国宝に指定された。
実は、貴金属で象嵌された太刀や利刀はいくつも出土している。
1 稲荷台1号墳出土の王賜銘鉄剣
2 稲荷山古墳出土の金錯銘鉄剣
3 江田船山古墳出土の銀錯銘大刀
4 岡田山1号墳出土の大刀
5 箕谷2号墳出土の鉄刀
6 東大寺山古墳出土の中平銘大刀
7 石上神宮伝世の七支刀
(Wikipediaより引用。)
その異なるのは、他の太刀は主君等から褒美にもらった太刀であり、刻まれている内容も太刀の由来や鍛冶作者銘であるのに対して、埼玉稲荷山古墳の金錯銘鉄剣は、持ち主が自分で依頼して作ったものであること、またその家系や職責や成果が事細かに刻まれていることなのである。
そこには100文字を超えるたくさんの漢文が刻まれていた。
同時期の鉄剣の多くは銀による象嵌がされており、錆びて文字が解読できなくなったり消えたりしているものが多いが、さすがはこの世界の価値の基準となったゴールドは全く経年劣化せずに1500年後にそこに刻まれた文字を一文字たりとも欠けることなく21世紀に伝えたのである。
そこには、日付が記されていた。
「辛亥年七月」
副葬品と干支表によると、471年、531年、591年、651年にあたり、5世紀から7世紀のどれかの年となる。
余談だが、西暦のように一意に判明する年表記を使っていたらこの後に示す問題は起きていなかっただろう。
刻まれていた漢文は100文字以上だが、問題なのは最後の44文字で、そこには次のように刻まれていた。

<金錯銘原文>
世々
為杖刀人首奉事
来至今(令)獲加多支鹵
大王寺(侍)在斯鬼宮
時吾左治天下
令作此百練利刀
記吾奉事根原也
<一般的な解釈>
世々、杖刀人の首と為り、奉事し来り今に至る。ワカタケルの大王の寺、シキの宮に在る時、吾、天下を左治し、此の百練の利刀を作らしめ、吾が奉事の根原を記す也
(鉄剣画像、一般的解釈はwikipediaより引用。)
この漢文解釈は専門家が導き出したものだ。
漢文というのは漢字だけで、句読点というものがない。
そのため、どこで改行するかどこが文節なのかの判断が正しい解釈のためには特に重要だ。
前に示した漢文は、私が改行を入れたものだ。
一般的に流通している文の区切りとは異なっていると思う。
最後の44文字を現代文に解釈すると次のようになる。
<新解釈>
代々、杖刀人の首長を為し奉りし
(このたび、ついに念願の)堅城を獲らしめるに至りき
斯鬼ノ宮に居られし大王に侍り
その時に吾れ、天下治むるを助くる
ここに百錬の名刀を作らしめ
吾が奉りしことがらを記すなりけり
一般的な解釈と大きく異なる点を取り上げてみよう。
(原文)
来至今(令)獲加多支鹵
(一般的解釈)
来り今に至る。ワカタケル
(私の新解釈)
(このたび、ついに念願の)堅城を獲らしめるに至りき
説明しよう。
・一般的解釈は文節が間違っている。
・「来至」と動詞を重ねているのは、新解釈にカッコ書きしているように「遂に、願いが成就し、成し遂げた」という強い思いを表している。
・「今」ではなく「令」である。
・「獲」は名詞の一部ではなく動詞である。
「獲加多支鹵」を日本書紀古事記の記述にある「雄略天皇の別名」の一部分と読みが同じだということをもって、「辛亥年七月」を471年であるとして、「5世紀にはすでに関東は奈良中央の支配を受けていたのだ。」と歴史を変えてしまった。
私は、日本書紀古事記に記載された25代までの天皇は嘘であると考えている。
ヤマトタケル、桃太郎、一寸法師らが、3世紀の古墳時代に日本アルプス(諏訪)を国の境界とするという協定を破り、我々が住む東国を侵略し始めたばかりの5世紀には、諏訪以東の関東東北は日本(ヒノモト)としてヤマトとは別の国であり、ヤマトの支配が関東に固着している時代ではない。
埼玉稲荷山古墳の主は、6世紀欽明天皇の時代(在斯鬼宮)に奈良中央にいて大王の側近として仕えた。
その後、東国に下り、以東の「毛人、エミシ」と呼びヤマトが蔑んだ縄文人の国ヒノモトと戦う最前線にいた首長となった。
591年(辛亥年)7月、命がけで戦っている中で、東国蝦夷の難攻不落の城を攻略できた。
その時の記念として大金をかけて剣に金で象嵌したのである。
自分が死ぬ時の副葬品を生前に作っておいたわけではないのである。
「獲加多支鹵」は「獲る」という動詞であり、「加多支鹵」は「堅城」という名詞なのである。
漢文というのは文節を変えるだけで解釈が全く変わるのだということに注意したいものである。