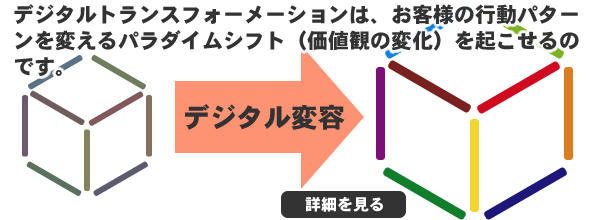古事記と日本書紀で国名ヤマトの漢字の当て字が異なるわけ
古事記それ自体その成立時期が怪しいのではあるが、その内容は9世紀の写本が現存する日本書紀とほとんど同じである。
万葉仮名の用いられ方から、序文以外の本文は6世紀には成立していたというのが有力である。
そこで重要になってくるのが、ヤマトという単語なのである。
「やまと」というと、現代人は日本文化を想像する。
そのヤマトに当てられた漢字が6世紀成立の古事記と8世紀成立の日本書紀で全く異なっている。
古事記では
「倭」
日本書紀では
「日本」
をそれぞれヤマトと読み仮名がふってあり、そう読ませたいようだ。
6世紀から8世紀にかけては飛鳥時代と呼ばれる時代にあたる。
この時期はヲワケ(継体天皇)が九州を平定(磐井の乱)した時期であり、大化改新という藤原氏のテロによって蘇我氏が滅亡した時期だ。
蘇我氏は馬子の時代に物部氏から「小さな体」であることを笑われている。また、エミシという名前をもつ人もいる。
風貌からして明らかに、渡来人としての弥生人が政治を仕切る以前に日本列島で政(まつりごと)をしていた縄文人と思われる。
飛鳥時代は、九州を都とするワから近畿を都とするヤマトに支配者が変わった時期なのである。
国名が倭(ワ)から日本(ヤマト)に変わる前に成立したのが古事記、日本に国名が変わった後に成立したのが日本書紀であり、ニホンショキではなくヤマトショキと当時は読んでいただろう。
現存する写本は9世紀以降のものなのであるから、古事記も日本書紀も国名の読み仮名はヤマトとふられている。
では、なぜ近畿のヤマトが「日本」という漢字を当てたのか?
近畿ヤマトは渡来人としての弥生人が主体となって作った国家だ。
ヤマトタケルやその後の征夷大将軍は近畿より東の国々を東征していった。
日本書紀が成立した9世紀の平安時代には東北をほぼ平定していた。
征夷大将軍の坂ノ上田村麻呂が蝦夷のアテルイを岩手で降伏させ、近畿ヤマトの東北征服のマイルストーンとなった時代だ。
その征服された蝦夷の国の名が日本(ヒノモト)だった。そして、その旗印は雪原に昇る朝日を意匠とした「白地に赤の日の丸」だったのである。