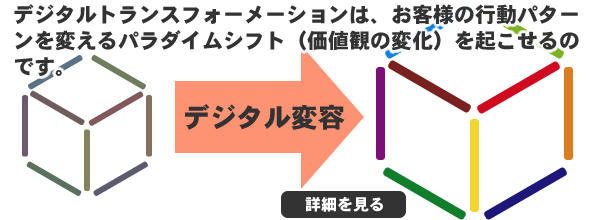聖徳太子としての蘇我馬子
聖徳太子としての蘇我馬子
蘇我馬子の親は稲目だが蘇我氏の家系では配偶者が全くわかっていない。
系図には親子関係しかないし、肖像画も残っていない。
蘇我氏は「馬子、蝦夷、入鹿」と名前の漢字の当て字に侮蔑が入っている。
藤原氏が蘇我氏をテロにより殺害し権力を握った後の記録しか現存していないため、当然といえば当然と言える。
蘇我馬子が「聖徳太子が行なったと学校教育してきた17条憲法の制定に代表される実績事項」を行ない、そして藤原氏の手で殺された、と私が考えるようになったかといえば、次のことが主な要因である。
藤原氏は大化の改新で蘇我氏を殺害してから平家政権ができるまでの300年もの間、日本の政治を牛耳っていた。
その藤原氏が聖徳太子の祟りを恐れ法隆寺を再建し聖徳太子を祀った。
藤原氏が上宮(厩戸王)を殺してもいないのに祟りを恐れるはずはない。
藤原氏が祟りを恐れるとしたら、それは蘇我氏以外にはありえない。
法隆寺夢殿には聖徳太子に生き写しと伝承される仏像があり明治時代まで誰も見たもののない秘仏だった。
救世観音菩薩像である。
それは、いわゆるステレオタイプの仏像ではない。具体的な誰かを見てあるいは想定して彫ったもので、喋り出しそうな雰囲気がある。
なぜ秘仏だったかといえば、その形相は他の聖徳太子像とは似ても似つかぬものだったからだ。
救世観音菩薩像こそ、蘇我馬子をモデルにした仏像だった。
あまりにも蘇我馬子に生き写しだったため、隠した。
厩戸王は蘇我馬子と二頭立で政権を運営していたと日本書紀には書かれているが、大王でもない20代の厩戸王が政策を立案したり取捨選択をすることはどんなに天才だったとしても無理である。
実際には、蘇我馬子が17条憲法を作り、遣隋使を送り、冠位12階を制定した。
日本書紀には大臣と書かれている馬子だが、実際には大門(ミカド)と呼ばれていた。
飛鳥時代6、7世紀、この時代は大王は九州にいた。
ヤマトには大王はいなかった。
そこにいたのは、倭の構成国の一つであるヤマト地方を統括する王の蘇我氏が支配する地域だった。
「日出処の天子、書を日没するところの天子に致す。恙きや。」
後にマンガや小説などの多くの歴史書で取り上げられた、この名言を藤原氏が編纂した日本書紀は全く触れていない。
その理由は、ヤマトの歴史ではなく倭國の歴史のため、9世紀の藤原氏はその事実を知らなかったのである。
天皇家と藤原氏は、この大化の改新を境に、権力を掌握し奈良・平安時代と我が世の春を謳歌していくのである。