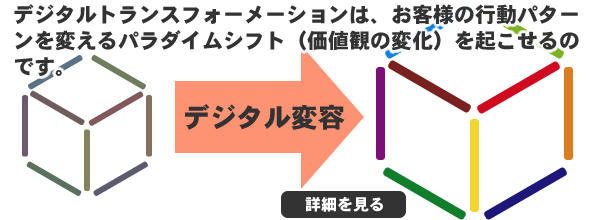トークンとは、資産・権威などの捉えにくい実体を文字・絵・図形などの意匠によってわかりやすく表したもの
「Token・トークン」という言葉を初めて知ったのは、トークンリングというEthernet 物理層にあたる通信方式だった。
通信権限であるトークンを取得できたら通信開始するという、いかにもクラッキングしやすそうなアーキテクチャだった。
インターネットの利用権限の取得は長らくIDとパスワードという時代が続いていたが、現在では20文字以下のパスワードは容易に解析できるようになってしまった。
(言い換えれば、悪意を持った第三者には20文字以下のパスワードはないのと同じ。)
また、パスワードは一箇所で漏洩してしまうと、同じIDの機密は全て漏洩してしまうという大きな問題があった。
特に、人にとって一番大事な「カネ」を直接的に扱う金融機関は、IDそれぞれと対応した乱数表によってパスワードを補完しようとした。
この乱数表は紙というメディアに固定的に印刷されたものであり、ほんの数桁の固定文字なので安全に利用権限を付与しているとはいえなかった。
そこで、暗号技術を使うことにした。
現在時間と付加情報とを利用者ごとの鍵により暗号しハッシュして、10桁ほどの数字のトークンに変換する。
ここで重要なのは、利用権限を付与するために突合する情報は、乱数表のそれとは異なり秘密にする必要が全くないことだ。
-
「トークンとは、資産・権威などの捉えにくい実体を文字・絵・図形などの意匠によってわかりやすく表したもの」である。
入場する権利という見えないものを、入場券というトークンによって第三者にもわかりやすくしたり
天皇などの王家の権威を示すために、その紋章や色を権威の象徴として配置したり
ある権限者による許諾を表すために、文面に対し、印章というそれを表す意匠をマークしたり、署名したりする。
これらが、トークンの機能を理解するための顕著な例である。
印影や署名といったアナログだからこその複製しにくさによって、この社会は成り立っていた。
インターネットによる通信は複製しやすさが長所なのであるから、印影や署名では「トークン(権威の代替)」を表現できない。
その唯一の方法が「暗号技術による計算式」と「十分な長さの任意の鍵」とを金融機関と利用者が双方で持ち、それから導いたお互いの計算結果を照合することによってトークンとしての機能を持たせたものなのである。
Ethereum Tokenは、通貨を信頼できる第三者なしにやり取りできるようにするためのトークン(通貨の代替)という意味である。