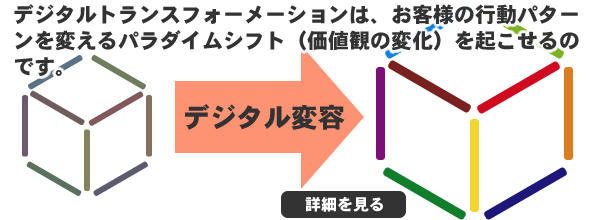iPhoneのSoCのアーキテクチャがARMからMIPSに変わったとしてもアプリ開発者は1日もかからずにMIPSで動作するアプリをAppStoreに並べることができる
IoTのことを考えていたら、数十年前のTronを思い出した。
東京大学で開発された純国産のOSだった。
その後紆余曲折があり、結局、家電製品への組み込み用途(embedded)でシェアを占めたことがあった。
しかし、Linuxに押され、21世紀の現在ではTronの名前を聞くことはほぼない。
SoCメーカは、ARMからそのライセンスを受けてARMアーキテクチャのSoCを生産し、スマホをはじめとするいろいろなデバイスに組み込んでいる。
SoCメーカがARMアーキテクチャを採用するのは、自社開発に比べてライセンスフィーが廉価だからだ。
IoTの世界であのIntelが使われないのは、一にも二にも電池消費の問題である。
ARMのライセンスフィーはコアあたり1000円ほどなのでICチップメーカも自社でICの設計を一から行うよりも安価なためARMのアーキテクチャを使っているだけで、特にARMを使わなければならないインセンティブは何もないのである。
主メモリを浪費する設計のAndroidOSを搭載したスマホだと4GBのメモリを搭載している機種さえ出てきている。
MIPSやAtomのアーキテクチャを採用したSoCを搭載したスマホも数パーセントはあるが、ほとんどのスマホにはARMアーキテクチャが採用されている。
いづれにしても、電池消費問題を解決するのはSoCではなく電池メーカーである。
現在主流のリチウムイオン電池から次のステージに進む必要があるだろう。
この問題は電池という限られたセグメントの問題ではなく、エネルギーメーカ全体で開発にしのぎを削っている。
自動巻腕時計というものが数十年前に存在したが、これと同じ仕組みによって、
15年後には、電池や電気エネルギーの残量を気にしたり、充電すら必要としなくなるだろう。
-
例えば、iPhoneが来年からSoCをMIPSアーキテクチャに変えるとアナウンスしたとしよう。
アプリ開発者は1日もかからずにMIPSで動作するアプリをAppStoreに並べることができるのだ。
データはクラウドに保存され、クラウド経由でアプリのダウンロードやアップデートを行うようになったコンピュータ環境においては、SoCのアーキテクチャはなんでもよく、そのときどきで都合の良いものを都合よく使えば良いのだ。
旧来のように電気店でパッケージに入ったDVDを購入する時代はとっくに終わっている。
20世紀のIntelのようにCPUの互換性を維持するためにリソースを割くような時代ではない。
したがって、今後ARMがIntelがそうであったように数十年間シェアを保つことはできないだろう。
SoCの設計は簡単であり、ハードウェアではなくソフトウェアといったほうが良い。
コンピュータメーカは、いつでも性能の良いSoCに乗り換えることができる環境にあるのだ。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
?スA?スv?ス?ス?スフ抵ソス?ス??
?スu?ス?ス?スb?スN?ス`?スF?ス[?ス?ス?ス^?ステ搾ソス?スZ?スp
?スV?ス?ス?ス?ス?スミ会ソス
?スT?スE?ス?ス謨ァ?ス?ス
?ス?ス?ス{?スフなりた?ス?ス