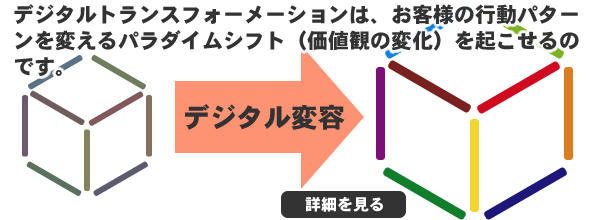意思の伝達手段としてのTelePhone(遠隔音声)はその立場を失った
明治から昭和にかけてTelePhone(遠隔音声)が家庭や企業に普及していった。
企業にとっては電話はどんな事業であっても、その事業を行う上でなくてはならないものという地位を占めるに至った。
明治時代の人は「telephone」を「電話」とよくも翻訳したなと思う。
この時代欧米諸国で"tele"という接頭語がつく発明品が相次ぐことになる。
TeleVisionSet
TeleGram
TeleCaster
中でもこの電話とテレビは20世紀の社会を変革するほどの大発明である。
私の祖父も父も商いを行なっていたので、黒い色をした電話は商売の重要な道具のひとつだった。
土足のまま入れる接客用の事務所があって、そこのソファで来客者と談笑している祖父の姿や土間に置いてある達磨ストーブで煮炊きした鍋料理を従業員に振る舞っている父の姿が目に浮かぶ。
TELEPHONEは遠く離れた人とも話せる道具として現れ、ほとんどすべての家庭と事業所に普及した。
発明してから90%超普及には100年かかっている。
近年まで6万円ほどの電話加入権を購入した人だけが電話局に電話線を引いてもらえるという意味で、電話番号は信用を担保する機能をも持っていた。
私がこの事業を始めた頃は連絡先として携帯電話番号だけを使うビジネスパーソンが増えてきた頃だったが、携帯電話番号を使う人や喫茶店で打ち合わせをしようという人は信用しなかった。
注文書はファクシミリ(FAX)で雛形を送り署名捺印したものを返信してもらっていた。
後払いが商習慣だったために、実在性や信用力が不明な相手と遠隔で取引きする仕事の焦げ付きを防ぐために少なくとも事業所があり電話回線を引いているということを確認するためだった。
現在ではエスクロー決済が普及し相手が実在していなくても良いのだし、相手が全く信用力がなくても取引する上で焦げ付く心配をする必要がないのである。
2017年現在、相手に意思を伝える手段は完全に電話からインターネットに取って代わった。
インターネットは電話がそれにかかった半分の期間で90%超普及した。その期間は50年ほどだ。
電話の前に普及していたテキストによる意思伝達手段として郵便というインフラがあった。
白い紙に文字の形にインクを染み込ませたものにサムネイルほどの有価証券を糊付けし、動物の死骸で作られた燃料を燃やして車輪を回転させてその紙を宅配していた。
相手に意思を伝えるためには、事前に思考し考えをまとめ場合によってはメモ帳に要点を書き留める。
そのあと、相手の電話番号を調べてダイヤルする。
相手が電話に出る確率は50%程度だった。
相手が企業の一員の場合には、その同僚が電話に出るが、相手が不在だと「電話があったことをお伝えください。」とか「折り返しお電話頂けるようにお伝えください。」として伝言をその同僚に頼むことになる。
そして、70年ぶりにPhone(音声)からText(テキスト)に意思伝達手段が取って代わった。
テキストとは、本でもなく文字でもない日本語には翻訳できない言葉である。
文字で表現したコンテンツを「テキスト」という。
特別な仕組みがない限り音声はその場で消えその場に居合わせた人のお互いの心の中にだけ存在する。
対してテキストというのは、人が声に出す前の段階の思考を紙や石や半導体や磁気記憶媒体に人が認識できる形式で保存したものである。
テキストは音声の様にその場で消え失せたりしない。
だから、人は推敲しながらテキストを作る。
25年後には、テキストの代わりに映像を送りあう社会が訪れるかもしれない。
しかし、iPhoneでビデオ通話ができてもほとんどの人は映像を相手に送って意思を伝える方法を選ばない。
絵文字がそうであるように、映像はテキストを保管する地位にしかなり得ないだろう。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
?スA?スv?ス?ス?スフ抵ソス?ス??
?スu?ス?ス?スb?スN?ス`?スF?ス[?ス?ス?ス^?ステ搾ソス?スZ?スp
?スV?ス?ス?ス?ス?スミ会ソス
?スT?スE?ス?ス謨ァ?ス?ス
?ス?ス?ス{?スフなりた?ス?ス