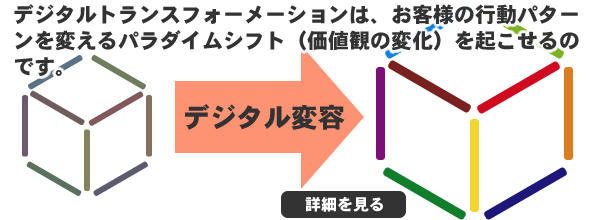イワレヒコ(初代天皇神武)の治世した年代は4世紀であることが判明
2017年11月12日
西暦600年、隋を訪問した倭国(日本国とは全く別の国である)の使者が天皇の名前とその子供の名前そして倭国の統治方法について言及している。(隋書)
倭国の国土は、東西は九州から伊勢湾まで、南北は福岡から阿蘇山を見ながら鹿児島までと記載されている。(隋書「其國境東西五月行南北三月行各至於海」)
不毛な邪馬台国論争をしているものは、古代は関門海峡はまだなく、九州は本州と地続きだったことを知るべきである。
(参考)古事記伝(本居宣長)
「上代には長門と豊前は続いた山で、その下に洞があって、潮の通う道があり、船も往来できないので穴戸と云った。」
-
倭国の天皇は阿毎多利思北孤(アマタリシヒコ)という名前で呼ばれ、自らは夜明け前に祈祷し天から神託を受け、日中の施政(政治)は弟に委任している。(隋書)
子供の名前は、和歌彌多弗利。
3世紀に書かれた三国志に記述されている女王卑弥呼による政治形態と同じように、卑弥呼から400年経った時代であるが同じく国政は弟に委任しているのである。(三国志)
この頃(1400年前)からすでにこの国(正確に言うとここ日本列島に存在していた国だが日本書紀を書いた日本国とは別の国)では天皇と将軍の例のように、権威と権力が乖離していたのである。
日本書紀にその名を尋ねると、5代天皇孝昭天皇の長男である天足彦国押人(アマタリシヒコ)という皇族がいた。
日本書紀ではこのアマタリシヒコは天皇になっていない。
代わりに弟の日本足彦国押人が6代天皇に就任したことになっている。
子供の名前は、和邇日子押人である。三国志に記載された名前(和歌彌多弗利)とも酷似していることが分かる。
倭国は1世紀から後漢と国交のあった連邦であり、3世紀には晋の使者が倭国を訪れている。(三国志)
倭国は九州から近畿までを国土としていた。
-
これまで見てきたように、6代孝安天皇の年代が6世紀であると比定された。
天皇1代を50年と長めにとったとしても、日本書紀が初代天皇としているイワレヒコが治世していた年代は辛酉の年であるので、4世紀(361年〜)であるということが分かる。
4世紀は、九州から近畿までを支配していた倭国においては、卑弥呼の直後に発生した倭国大乱(2世紀)の後の女王である豊が大王であった時代の100年後にあたる。(三国志)
645年に連邦である倭国の王(大王ではない)の一人としてヤマト(近畿地方)を治めていたミカドの蘇我氏を中臣(藤原氏)がテロで殺害した事件以降に、現在の天皇に至るいわゆる「万世一系」の流れができた。
この大化改新(乙巳の変)といわれる事件で、政権交代が起きたことで、現存していた倭国による「天皇記・国記」等を焼却し、新たに「日本書紀」を作成し、政権の正統性をうたった。
そのため、日本書紀全30巻のうち、25巻まで(神武〜孝徳・大化改新を含む7世紀半ばまで)の記述は潤色したものと言われているが、作成者の藤原氏によるほぼウソと言ってよい。
その後、倭国連邦の所属国であったヤマト国が倭国連邦を支配していた邪馬台国を打ち破り、倭国と名のった。
そして、日本アルプス以東を支配していた縄文人の国である日本国(ヒノモトノクニ、ヤマトから「毛人の国」と呼ばれていた)との協定(諏訪大社の御柱以東には侵入しない)をヤマト国が一方的に破り、日本国を侵略し、奈良時代にはその国の名をも奪い、日本国の読み方を中国風に「ニッポンコク(またはニホンコク)」とし、現在に至るのである。
<参照>
この国(日本国)の名前が訓読みではなく、なぜ音読み(中国読み)なのかをよく考えるべきである。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち