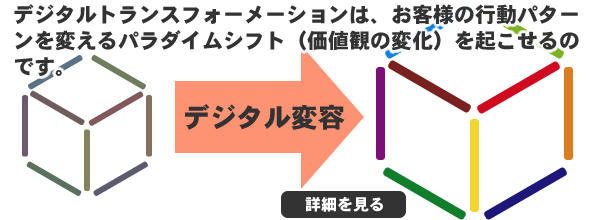【概要編】なぜブロックチェーン・システムにおいては信頼できる第三者が必要ないのか?
P2P(ピアツーピア)という技術は、90年代、個人間でファイル共有したり、音声通話したりというホビーユースな使われ方が主体だった。
なぜかといえば、ホストとターミナルの時代も、サーバとクライアントの時代でも、そしてクラウドとブラウザになっても、重要なことは信頼できる第三者が停電やクラッキングや地震や戦争に備えた設備を整えて、システムを多重化し、バックアップを毎日行い、システムログを常に監視するために、想像できないくらい高額なランニングコストをかけて運用している。
それにひきかえ、P2Pはいつ壊れてもおかしくない安価なパソコンやスマホやタブレットで構成されており、信頼できない (良き人か悪意を持っているかがわからないという意味)一般人が運用している。
銀行システムに代表されるミッションクリティカルなシステムはP2Pではとても運用できないと考えられてきた。
しかし、2008年に突如として一人の日本人が「ブロックチェーン」の概念とそれを実装したコードを公開、データの破壊もウイルス被害も不正アクセスされたとしても、データが保全できるという暗号の特性と社会科学を応用した解決法である「Proof-of-Work」を利用した「自然科学の賜物であるコンピュータ・システムに社会科学を持ち込んだアーキテクチャ」によって、システムを多重化する必要もない、バックアップを毎日行う必要もない、システムログを常に監視する必要もない、システムを維持するためのランニングコストが全くかからないシステムがP2Pで実現できることを証明した。
そのエポックから10年が経ち、事実(9年間問題なく通貨決済システムを運用できたという実績)が「Proof-of-WorkブロックチェーンP2Pネットワーク」の確かさを証明し、欧州を中心にブロックチェーン技術を活用したP2Pシステムが商用段階に入ったところなのである。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
?スA?スv?ス?ス?スフ抵ソス?ス??
?スu?ス?ス?スb?スN?ス`?スF?ス[?ス?ス?ス^?ステ搾ソス?スZ?スp
?スV?ス?ス?ス?ス?スミ会ソス
?スT?スE?ス?ス謨ァ?ス?ス
?ス?ス?ス{?スフなりた?ス?ス